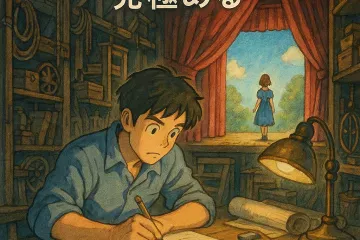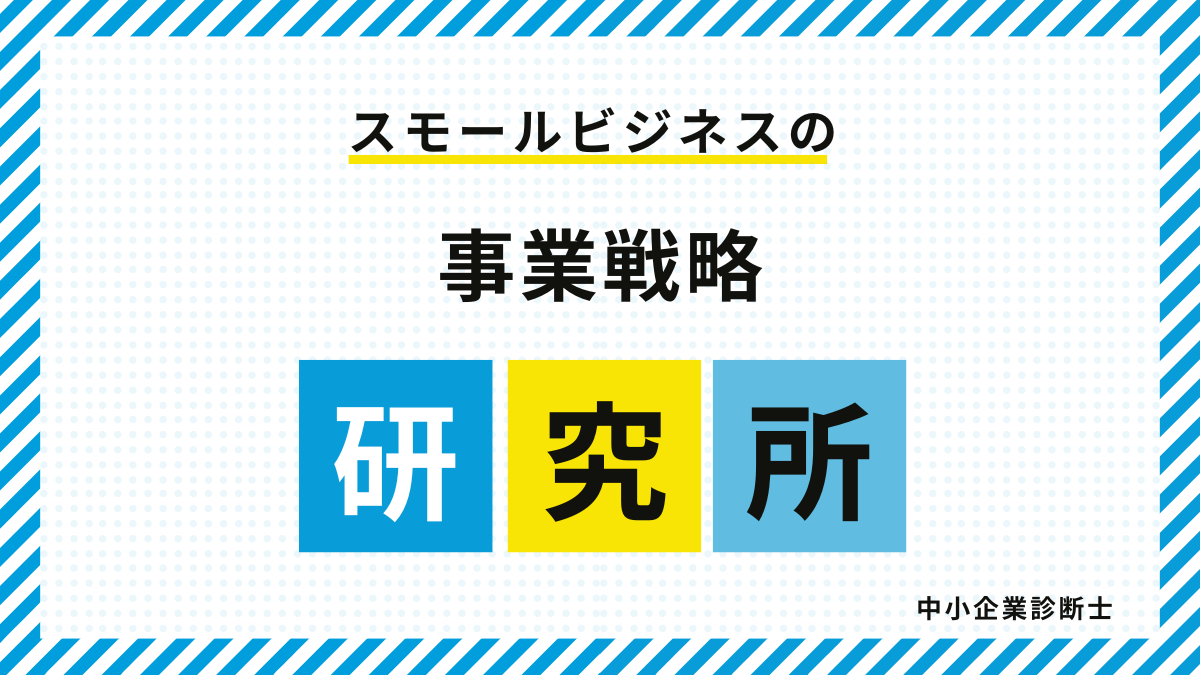
どんなに素晴らしい価値提案(VP)も、それが顧客に届かなければ意味がありません。そして、一度繋がった顧客との関係をどう育むかが、事業の持続的な成長の鍵を握ります。
皆さんこんにちは!事業構想×生成AI活用アドバイザー(中小企業診断士)の津田です。
前回(第6回)は、競合という「鏡」を覗き込み、恐れるのではなく学びを得て、自社だけの「違い」を磨き、「選ばれる理由」を創り出す方法を探求しました。
さて、自分たちの事業が進むべき独自の仕組みが見えてきたところで、次なる課題は「どうやって、その価値を顧客に伝え、認知から購入までの経路を用意し、そして末永く良い関係を築いていくか?」ということを考えていきます。
今回は、ビジネスモデルキャンバス(BMC)の右側、顧客との接点を司る二つの重要なブロック、「チャネル(CH)」と「顧客との関係(CR)」に焦点を当てます。
この二つを効果的に設計し、連携させることが、事業の価値を顧客に届け、心を掴むための核心です。
目次
1. はじめに 『どう届け』『どう繋がるか』が価値を決める
これまでの回で、自社の「強み」を発見し、「顧客(ペルソナ)」を深く理解し、顧客に響く「価値提案」を創り上げ、競合との「違い」を明確にしてきました。そしてBMCで事業の骨格も見えてきました。
しかし、どんなに素晴らしいエンジン(価値提案)や設計図(BMC)があっても、顧客という「乗客」を船に乗せ、快適な航海を提供するための「経路」や「おもてなし」がなければ、船は港を出ることすらできません。
- チャネル(CH)は、あなたの価値を顧客に「届ける経路」であり、顧客があなたと出会い、関わるための「接点」です。
- 顧客との関係(CR)は、その接点を通じて顧客と「どのような繋がり方をし、それをどう維持・発展させていくか」という「関係性のスタイル」です。
この二つは、単なる「販売方法」や「顧客対応」といった個別の活動ではありません。
顧客があなたのビジネスに触れるあらゆる瞬間を形作り、最終的な「顧客体験(カスタマージャーニー)」そのものを左右する、極めて重要な要素です。
今回は、このチャネルと顧客との関係をどう設計し、連携させていくか、具体的な考え方を見ていきましょう。
2. チャネル(CH)編:価値を顧客に届ける『多目的経路』を組み立てる
まずは、顧客に価値を届ける「経路」、チャネル(CH)についてです。
2-1. チャネルを広げる
チャネルと聞くと、「商品を売る場所(店舗やECサイト)」を思い浮かべるかもしれません。
しかし、BMCにおけるチャネルはもっと広範です。
それは、顧客があなたのビジネスを知り、関心を持ち、購入し、そして購入後も関わり続ける全ての接点を指します。
大きく分けると、チャネルには二つの側面があります。
- 情報・コミュニケーションの経路
顧客にあなたの存在や価値を知ってもらい、興味を引き、評価してもらうための接点。(例:広告、SNS、ブログ、口コミ、セミナー、相談会)
- 価値提供・商流の経路
顧客が実際に商品やサービスを購入し、受け取り、利用し、サポートを受けるための接点。(例:店舗、ECサイト、営業担当、配送、アプリ、サポート窓口)
これらを区別して考えることが、効果的なチャネル設計の第一歩です。
2-2. 顧客が旅する5つの段階
顧客があなたのビジネスと関わるプロセスは、一般的に以下の5つの段階(フェーズ)で考えることができます。
それぞれの段階で、チャネルは異なる役割を果たします。
① 認知 (Awareness)
どうやって、あなたの存在をターゲット顧客に知ってもらいますか?
② 評価 (Evaluation)
どうやって、あなたの価値提案の良さを理解・判断してもらいますか?
③ 購入 (Purchase)
どうやって、顧客がスムーズに購入できるようにしますか?
④ 提供 (Delivery)
どうやって、約束した価値を確実に届けますか?
⑤ アフター (After Sales)
購入後、どのように顧客をサポートし、満足度を高め、関係を継続しますか?
あなたのビジネスでは、これらの各段階で、現在どのようなチャネルを使っていますか?
あるいは、これから使おうと考えていますか?
2-3. 経路の種類は自社直接か?パートナー経由か?オンラインか?オフラインか?
チャネルには様々な種類があります。大きく分けると以下のようになります。
- 自社チャネル:自分たちで直接運営するチャネル(例:自社Webサイト/EC、直営店、自社営業チーム)
- メリット:利益率が高い、ブランドコントロールしやすい、顧客データを直接収集できる。
- デメリット:立ち上げ・維持コストがかかる、リーチ拡大に限界がある場合も
- パートナーチャネル: 他社と協力して活用するチャネル(例:卸売業者、小売店、代理店、アフィリエイト、オンラインマーケットプレイス)
- メリット:広範囲なリーチ、立ち上げコストが低い場合がある、パートナーのブランド力を活用できる。
- デメリット:利益率が低い、ブランドコントロールが難しい、顧客接点が間接的になる。
また、これらのチャネルは、オンライン(Webサイト、SNS、アプリなど)とオフライン(店舗、イベント、電話など)に分けられます。現代では、多くの場合、オンラインとオフラインを効果的に組み合わせる(OMO: Online Merges with Offline)ことが重要になっています。
2-4. 『目的』別チャネル設計術:自分で経路を組み立てる思考法
さて、ここが重要です。多種多様なチャネル手法の中から、どれを選び、どう組み合わせれば良いのでしょうか?
まさに「自分で経路を組み立てる」ための考え方です。
ポイントは、『目的』と『ターゲット顧客(ペルソナ)』に合わせて手法を戦略的に選ぶことです。
ステップ1:各フェーズの『目的』を明確にする。
■「認知」段階なら、目的は「とにかく多くのターゲット顧客に名前を知ってもらうこと」かもしれません。
■「評価」段階なら、「製品の良さを深く理解し、信頼してもらうこと」が目的でしょう。
ステップ2:ターゲット顧客(ペルソナ)の『行動・好み』を考える。
■あなたのペルソナは、普段どこで情報を得ていますか?(SNS? 業界誌? 口コミ?)
■どんな方法で商品・サービスを比較検討しますか?(Webサイトでじっくり? 実物を見たい?)
■どんな購入方法を好みますか?(手軽なオンライン決済? 対面での相談?)
ステップ3:目的に合い、顧客に届く『手法』を選ぶ・組み合わせる。
例(認知目的なら)
若年層向けならSNS広告やインフルエンサーマーケティング、BtoBなら業界展示会や専門メディアへの露出、地域密着型ならチラシや地域イベントへの出展などが考えられます。
例(評価目的なら)
詳細な情報を提供するWebサイト、導入事例や顧客の声、無料トライアル、製品デモ、体験セミナー、個別相談会などが有効です。
例(購入~アフターまで)
スムーズな決済が可能なECサイト、丁寧な接客の店舗、迅速な配送体制、分かりやすいマニュアル、アクセスしやすいサポート窓口、購入者限定コミュニティなどが考えられます。
「どの段階で」「誰に」「何を達成したいか」を常に考え、それに最適なチャネル手法をパズルのように組み合わせていく。これがチャネル設計の基本です。
最初から完璧を目指さず、試行錯誤しながら最適化していくことが大切です。
2-5. 【AI活用ヒント】:チャネル戦略の精度を高める
- ターゲット顧客のチャネル利用状況調査
「[ターゲット顧客層]が情報収集や購買によく利用するオンライン/オフラインチャネルは何ですか? 最新の調査データや傾向を教えてください」とAIに尋ね、仮説の精度を高める。
- 効果的なメッセージング案
特定のチャネル(例:SNS広告)で、ターゲット顧客に響くキャッチコピーやメッセージの案をAIに複数提案してもらう。
3. 顧客との関係(CR)編:顧客と『心』で繋がり続ける方法を探る
チャネルを通じて顧客と出会えたら、次はどんな「関係性」を築いていくか、顧客との関係(CR)について考えます。
3-1. なぜ繋がる?関係構築の『価値』とは
一度獲得した顧客との関係を良好に保つことは、なぜ重要なのでしょうか?
■LTV(顧客生涯価値)の向上
顧客が長期にわたってあなたの商品・サービスを繰り返し利用(リピート購入、アップセル、クロスセル)してくれることで、一人あたりの顧客から得られる総利益が増加します。
■安定収益の基盤
熱心なファン(ロイヤルカスタマー)は、景気変動などに左右されにくい安定した収益基盤となります。
■口コミ・紹介による新規顧客獲得
満足度の高い顧客は、友人や知人にあなたのビジネスを推薦してくれる、強力な「広告塔」になってくれます。
■新規顧客獲得コストの削減
一般的に、既存顧客を維持するコストは、新規顧客を獲得するコストよりも低いと言われています。
つまり、良好な顧客関係は、短期的な売上だけでなく、長期的な事業の安定と成長に不可欠なのです。
3-2. 関係性のスタイルを知る:どんな繋がり方がある?
顧客との関係性には、様々な「スタイル」があります。代表的なものをいくつか見てみましょう。
■人的支援 (Personal Assistance)
顧客一人ひとりに担当者がつき、個別に対応する手厚い関係。(例:BtoB営業、高額商品のコンシェルジュ、顧問サービス)
■セルフサービス (Self-Service)
顧客自身が必要な情報やサポートを得られるようにする関係。(例:FAQサイト、オンラインマニュアル、注文システム)
■自動化されたサービス (Automated Services)
テクノロジーを活用し、個別化されたサービスや情報を提供する関係。(例:ECサイトのレコメンド機能、パーソナライズされたメールマガジン)
■コミュニティ (Communities)
顧客同士や企業と顧客が交流できる場を提供し、帰属意識や愛着を育む関係。(例:オンラインフォーラム、ユーザーグループ、ファンイベント)
■共創 (Co-creation)
商品開発やレビュー投稿など、顧客に価値創造プロセスに参加してもらう関係。(例:レビューサイト、アイデア募集、ベータテスト)
これらは独立しているわけではなく、組み合わせて使われることも多くあります。
3-3. 『誰と、どんな関係を』目指すか?選び方のヒント
では、あなたのビジネスでは、どのスタイルを目指すべきでしょうか? 以下の点を考慮して選びましょう。
■顧客セグメント(CS)の期待
あなたのターゲット顧客は、どんな関係性を期待しているでしょうか?(手厚いサポートを求めている? それとも、干渉されずに自由にやりたい?)
■価値提案(VP)の性質
提供する価値は、個別のアドバイスが必要な複雑なものですか? それとも、シンプルで分かりやすいものですか?
■コスト
関係性を維持するためにはコストがかかります。人的支援は高コストですが深い関係を築けます。自動化やセルフサービスは低コストですが、人間的な温かみは出しにくいかもしれません。事業の収益性とのバランスが重要です。
■ブランドイメージ
あなたが目指すブランドイメージ(例:親しみやすい、専門的、革新的)と、関係性のスタイルは一致していますか?
全ての顧客に同じ関係性を提供する必要はありません。顧客セグメントによって、あるいは顧客の利用状況によって、関係性のスタイルを変えることも有効な戦略です。
3-4. 関係性を『カタチ』にする活動
目指す関係性のスタイルを決めたら、それを実現・維持するために具体的に何をすべきかを考えます。
■人的支援なら
担当者の教育、CRM(顧客関係管理)システムの導入、定期的な連絡
■セルフサービスなら
分かりやすいFAQやマニュアルの整備、検索性の向上
■自動化なら
MA(マーケティングオートメーション)ツールの導入、データ分析に基づいたシナリオ設計
■コミュニティなら
プラットフォームの選択、運営ルールの策定、活性化のための企画(イベント、情報提供)
■共創なら
レビュー機能の実装、アイデア投稿フォームの設置、参加者へのインセンティブ設計
これらの活動には、当然ながらリソース(ヒト・モノ・カネ)が必要です。ビジネスモデル全体の中で、無理なく継続できる計画を立てることが重要です。
3-5. 【AI活用ヒント】:顧客との絆を深める
■パーソナライズされたコミュニケーション支援
顧客データに基づき、AIが個々の顧客に合わせたメールやメッセージの文面案を作成し、One to Oneの関係構築を支援する。
■顧客の声の感情分析
サポートへの問い合わせ内容やレビューをAIが分析し、顧客の感情(満足、不満、要望など)を把握。関係改善のヒントを得る。
4. 連携が鍵!最高の顧客体験は『チャネル×顧客との関係』から生まれる
ここまで、チャネル(CH)と顧客との関係(CR)を個別に見てきました。しかし、最も重要なのは、この二つが『連携』して機能することです。
✅️選んだチャネルは、あなたが築きたい顧客との関係を実現できるものになっていますか?
(例:コミュニティを重視するなら、交流しやすいオンラインプラットフォームというチャネルが必要)
✅️目指す顧客との関係は、選択したチャネルを通じて効果的に提供できますか?
(例:手厚い人的サポートを提供したいのに、チャネルがWebサイトしかない、というのは無理があります)
チャネルと顧客との関係は、車の両輪のようなものです。片方だけが優れていても、もう片方がうまく機能していなければ、顧客体験は損なわれ、ビジネスは前進しません。
広告(CH)で素晴らしい第一印象を与えても、問い合わせ(CH)への対応(CR)が悪ければ台無しです。
素晴らしい商品(VP)を開発しても、それを顧客が簡単に入手できる経路(CH)がなければ売れません。
あなたのビジネスの全ての顧客接点(CH)において、一貫した関係性のスタイル(CR)を提供し、顧客がスムーズで心地よい「旅(ジャーニー)」を体験できるように設計すること。
これが、顧客の心を掴み、長期的なファンになってもらうための鍵なのです。
5. Miraizと設計支援:最適な『経路』と『繋がり』を共に描く
「チャネルと顧客との関係、考えることが多くて整理できない…」 「自社にとって最適な組み合わせが分からない…」 「どうすれば一貫した顧客体験を設計できるんだろう?」
私たちMiraizは、こうした課題に対し、専門的な知見とAIの分析力を駆使して、あなたに最適なチャネル戦略と顧客関係構築の設計をサポートします。
■顧客視点でのジャーニー設計
あなたのペルソナが、認知から購入、そしてファンになるまでのプロセス(カスタマージャーニー)を具体的に描き出し、各段階で最適なチャネル(CH)と関係性(CR)の組み合わせを検討します。
■BMC全体との整合性
設計したCHとCRが、価値提案(VP)、顧客セグメント(CS)はもちろん、キーリソース(KR)やコスト構造(CS)といったビジネスモデルの他の要素とも矛盾なく連携しているか、客観的に検証します。
■AIによる選択肢の提示と分析
様々なチャネル手法や関係構築のベストプラクティスについて、AIが情報提供や分析を行い、より効果的で効率的な選択を支援します。
私たちは、単に要素を当てはめるだけでなく、あなたのビジネスの独自性と顧客への想いを反映した、実行可能で心に響く「経路」と「繋がり」の設計図を、あなたと共に創り上げます。
6. まとめと次回(第8回)予告
今回は、ビジネスモデルの顧客接点を司る「チャネル(CH)」と「顧客との関係(CR)」について、その設計方法と連携の重要性を探求しました。
- チャネルは、情報伝達と価値提供の多目的経路であり、5つのフェーズと目的を意識して組み立てる。
- 顧客との関係は、LTV向上に不可欠であり、顧客や価値提案に合わせてスタイルを選ぶ。
- チャネルと顧客との関係は密接に連携し、一貫性のある設計が最高の顧客体験を生む。
これで、あなたの価値を「誰に(CS)」「何を(VP)」、「どのように届け(CH)」「どのように繋がるか(CR)」という、BMCの右半分、顧客サイドの設計がかなり明確になったはずです!
さあ、船の設計図(BMC)の右側が固まってきたところで、いよいよ船を動かすための燃料、すなわち『収益』について考える時が来ました。
次回、【第8回】「価値をお金に変える:収益モデルの設計」では、あなたが提供する素晴らしい価値に対して、顧客からどのように対価をいただき、ビジネスとして成立させていくのか? その具体的な「稼ぎ方=収益モデル」の設計方法を探っていきます。
顧客との素晴らしい関係を築く準備はできましたか? 次回は、その関係を持続可能にするための「お金」の話です。どうぞお楽しみに!