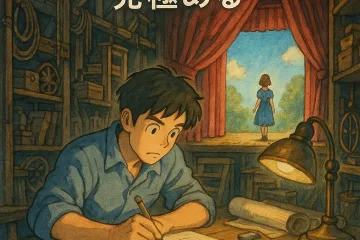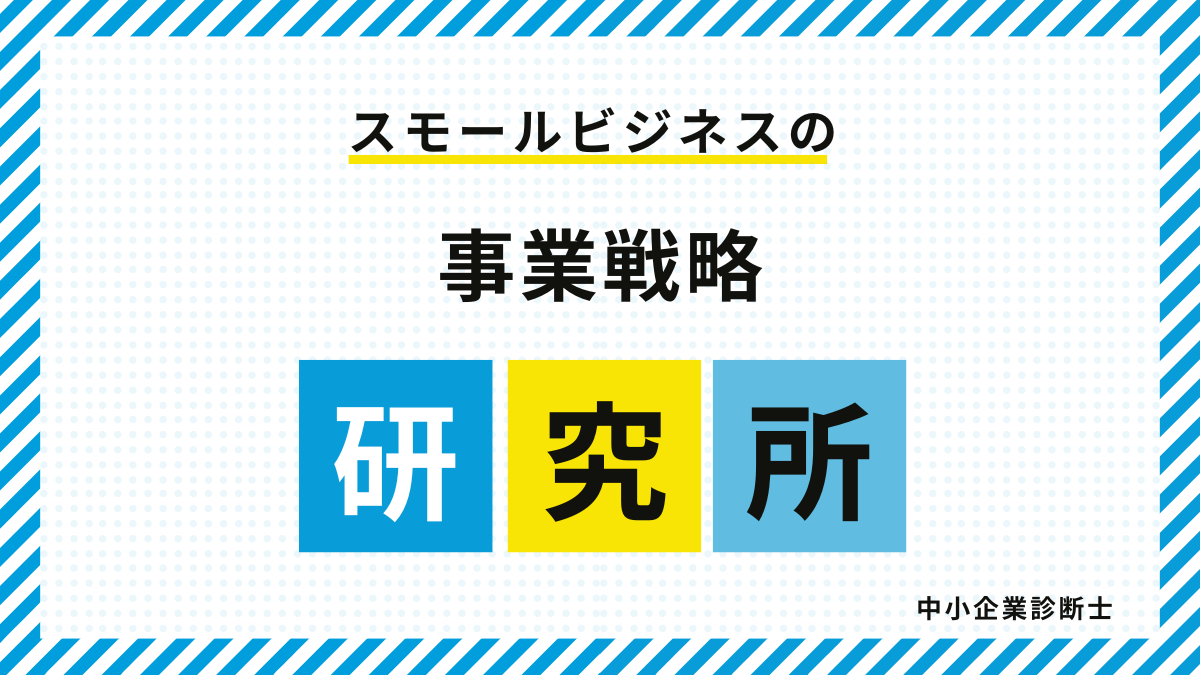
自分(自社)の持つ強みで「誰に魅力をお届けするか」お客さんは誰ですか?
今回のテーマは、事業構想の核となる『顧客理解』です。あなたの価値を本当に必要としている、未来のお客様を考えていきましょう。
皆さんこんにちは、事業構想×生成AI活用アドバイザー(中小企業診断士)の津田です。
前回(第2回)では、あなた(自社)の中に眠る「強みの元」を発見するための具体的なアプローチについてお話ししました。
自分たちの持つ武器や装備が見えてきたところで、次なる重要な問いは「その武器を、いったい『誰』のために使うのか?」です。
実は、この「顧客理解」、多くの経営者や創業者が陥りやすい「罠」があるのをご存知でしょうか?
目次
1.あなたの顧客は「誰」ですか? ~属性だけ見ていませんか?~
事業を考える上で「ターゲット顧客は誰ですか?」という問いは、避けて通れません。
しかし、ここでよくあるのが、「うちの顧客は、まあ、幅広く…」と考えてしまう「顧客を広く捉えすぎる罠」。
これでは、結局誰にも響かない、ぼんやりとしたアプローチになりがちです。
そして、もう一つ、より巧妙な罠があります。
それは、「顧客を『属性』(年齢・性別・地域・年収など)だけで捉えてしまう罠」です。
「うちのターゲットは、都内在住の30代女性です!」 「年収〇〇万円以上の富裕層向けサービスです!」
一見、具体的で明確なように聞こえます。もちろん、こうした属性情報も重要です。
しかし、本当にそれだけで、あなたの顧客の「顔」が見えていると言えるでしょうか?
このブログでは、属性情報だけでは見えてこない、顧客の「本質」を理解するための考え方と、具体的な方法について掘り下げていきます。
2. なぜ「属性」だけでは顧客を理解できないのか?
考えてみてください。同じ「40代男性・会社員・既婚・子供2人」という属性の人でも、その内面は千差万別です。
- Aさんは、仕事で昇進を目指し、自己投資に積極的。休日は家族サービスも欠かさないが、自分の趣味の時間も大切にしたい。
- Bさんは、ワークライフバランスを最優先。仕事はそこそこに、家族との時間や地域の活動に多くの時間を費やしたい。節約志向が強い。
もしあなたが、このAさんとBさんに同じ商品やサービスを、同じメッセージで届けようとしても、おそらくどちらにも深くは響かないでしょう。
なぜなら、彼らが「何に悩み」「何を望み」「何を大切にしているか」が全く異なるからです。
属性情報は、顧客の「外側のラベル」を示すことはできても、その人が「なぜ、あなたの商品やサービスを選ぶ(あるいは、選ばない)のか?」という行動の根本的な動機を教えてはくれません。
そして、効果的な価値提案や商品開発、心に響くメッセージ作りは、この「動機」を理解することなしには成り立たないのです。
3. 顧客理解の鍵は「ジョブ(Jobs To Be Done)」にあり!
では、顧客の「動機」や「本質」を理解するには、どうすれば良いのでしょうか?
その強力なヒントとなるのが、「ジョブ理論(Jobs To Be Done: JTBD)」という考え方です。
これは、「顧客は、特定の状況において、何か『進歩(Progress)』をしたい、あるいは『片付けたい用事(Job)』があるから、その『手段』として商品やサービスを『雇う(Hire)』のだ」と捉える考え方です。
有名な例え話があります。「ドリルを買う人が本当に欲しいのは、ドリルという『モノ』ではなく、それによって得られる『穴』である」。
さらに言えば、「穴」を開けることで、「棚を取り付けたい」「快適な生活空間を作りたい」といった、より本質的な「ジョブ」を片付けようとしているのかもしれません。
つまり、顧客を理解する上で重要なのは、
- 顧客がどんな状況で(When)
- どんな「悩み・不満・困りごと」(Pain)を解決したいのか?
- あるいは、どんな「理想・願望・得たい快感」(Gain)を実現したいのか?
といった、顧客が抱える『ジョブ』を具体的に見つけ出すことなのです。
この『ジョブ』こそが、顧客があなたの商品やサービスに手を伸ばす、根本的な理由となります。
さらに、顧客が片付けたい「ジョブ」には、大きく分けて3つの側面があると言われています。
これらを意識することで、顧客の動機をより深く理解できます。
機能的ジョブ (Functional Job)
・特定のタスクを完了させたい、問題を効率的に解決したい
といった実用的な目的
「時間通りに目的地に着きたい」「美味しいコーヒーを手軽に淹れたい」「部屋をきれいに保ちたい」
感情的ジョブ (Emotional Job)
・特定の感情を感じたい(例:安心したい、ワクワクしたい、自信を持ちたい)
・特定のネガティブな感情を避けたい(例:不安を減らしたい、罪悪感を持ちたくない)
といった心理的な目的
「この服を着て気分を上げたい」「この保険に入って将来の不安を和らげたい」などが考えられます。
社会的ジョブ (Social Job)
・周りの人から特定の見られ方をしたい(例:良い親だと思われたい、環境意識が高い人だと見られたい)
・特定の社会集団に属したい、あるいは特定の社会的役割を果たしたい
といった社会的な目的
「このブランド品を持つことで、ステータスを示したい」「このエコ製品を使うことで、社会貢献していると感じたい」などが例として挙げられます。
多くの場合、顧客はこれらのジョブを複合的に抱えています。
そして、特に感情的ジョブや社会的ジョブが、最終的な購買決定に大きな影響を与えることも少なくありません。
あなたの顧客は、機能的な目的だけでなく、どんな感情的・社会的なジョブを片付けようとしているでしょうか?
4. 顧客の「ジョブ」を発見する具体的な方法
では、どうすれば顧客の「ジョブ」を発見できるのでしょうか? いくつかのアプローチがあります。
■顧客インタビュー
「普段、どんなことで困っていますか?」
「〇〇をする時、何が一番面倒だと感じますか?」
「もし何でもできるなら、何を解決したいですか?」
といったオープンな質問を通じて、顧客の本音や潜在的なニーズを探ります。
(機能的・感情的・社会的ジョブの視点からも質問してみましょう)
■行動観察
顧客が実際にあなたの商品やサービスを使っている場面(あるいは、競合製品を使っている場面)を観察します。
どんな使い方をしているか、どんな表情をしているか、どんな工夫や不満のサインが見られるか。
言葉にならないニーズを発見できることがあります。
■レビュー・口コミ分析
顧客が自発的に発信するオンライン上のレビュー、SNSの投稿、お客様の声などは、「生々しい本音」の宝庫です。
特に、具体的な不満点や、逆に「こんなところが最高!」と絶賛されているポイントには、重要な「ジョブ」のヒントが隠されています。
■AI活用で「ジョブ」のヒントを掴む
大量の顧客の声や市場データを効率的に分析し、「ジョブ」の仮説を立てる上で、生成AIは強力な武器になります。
① 顧客の声から「進歩」を抽出する(プロンプト例)
# 命令
あなたは顧客インサイトのアナリストです。
以下の顧客レビュー(またはSNS投稿の抜粋)から、「顧客が抱えている悩み・不満・ペイン」と「顧客が望んでいること・期待・ゲイン」に関するキーワードや具体的な記述を抽出・要約してください。可能であれば、それらが機能的・感情的・社会的ジョブのどれに関連しそうかも示唆してください。特に多く言及されているテーマがあれば、それも指摘してください。
# 分析対象データ
[ここに顧客レビューやSNS投稿のテキストデータを貼り付け(複数可)]
# 出力形式
* 悩み・不満・ペインに関する記述(関連ジョブ側面):箇条書き
* 望み・期待・ゲインに関する記述(関連ジョブ側面):箇条書き
* 特に多く見られるテーマ(もしあれば):
使い方ポイント
■ 大量のテキストデータから、ニーズの種となるキーワードや感情表現を効率的に見つけ出すことができます。
■ 個人情報には十分注意し、匿名化するなどの配慮が必要です。AIの示唆はヒントとして捉えましょう。
② 特定顧客層の「ジョブ」について壁打ちする(プロンプト例)
# 命令
あなたは経験豊富なマーケターであり、ジョブ理論に詳しい専門家です。
私がターゲットと考えている以下の顧客層について、彼/彼女らが日常生活や仕事において抱えていそうな「解決したい悩み(ペイン)」や「実現したい望み(ゲイン)」、つまり「片付けたい用事(ジョブ)」の仮説を、できるだけ具体的に、複数提案してください。
その際、機能的・感情的・社会的ジョブの3つの側面から考えてください。
私との壁打ちを通じて、より深い顧客理解を目指しましょう。
# ターゲット顧客層
* 属性:[例:都内在住、30代共働き夫婦、子供(保育園児)1人]
* ライフスタイルや価値観(推測):[例:仕事と育児の両立に奮闘、時間は限られている、子供の教育に関心が高い、安心・安全を重視]
* その他情報(もしあれば)
# 提案の視点
* 機能的ジョブ(どんなタスクを達成したいか?)
* 感情的ジョブ(どんな気持ちになりたいか?避けたいか?)
* 社会的ジョブ(どう見られたいか?どんな役割を果たしたいか?)
* そのジョブを片付けるために、現在どのような代替手段を使っている可能性があるかも推測してください。
使い方ポイント
AIに仮説を出してもらうことで、自分の思い込みだけでは気づかなかった顧客の「ジョブ」を発見するきっかけになります。
AIの回答を元に、「なぜそう言えるのか?」「もっと具体的には?」「どのジョブが一番重要そうか?」とさらに深掘りしていく対話が重要です。
5. 「ジョブ」を持つ顧客像を具体化する「価値中心ペルソナ」の作り方
顧客の「ジョブ」が見えてきたら、次はそのジョブを抱える具体的な顧客像=「ペルソナ」を描いてみましょう。
ペルソナとは、あたかも実在する人物かのように、氏名、年齢、職業、ライフスタイル、価値観、そして抱える「ジョブ」などを詳細に設定した、架空の顧客像のことです。
ペルソナを設定することで、
- チームメンバー間で「私たちの顧客はこういう人だ」という共通認識を持てる。
- 顧客の視点に立って、商品開発やマーケティング施策を考えられる。
- メッセージがブレなくなり、顧客に「私のための商品だ!」と感じてもらいやすくなる。
といったメリットがあります。
ただし、ここで注意したいのが、単なる属性情報の寄せ集めにならないようにすること。
重要なのは、発見した『ジョブ(進歩)』を中心に据え、そのジョブを持つ人物像をリアルに描き出す「価値中心ペルソナ」を作成することです。
「価値中心ペルソナ」作成のステップ(例)
1.発見した主要な「ジョブ」を特定する
あなたが解決したい顧客の「悩み」や「望み」は何か?(機能的・感情的・社会的側面も考慮)
2.【AI活用】ペルソナの骨子案を作成してもらう
特定したジョブや、想定される顧客層に関する情報をAIに与え、具体的なペルソナの「叩き台」を作成してもらうことができます。
これにより、ゼロから考える手間が省け、より多様な視点を取り入れやすくなります。
ペルソナ作成支援プロンプト例
# 命令
あなたは経験豊富なマーケターであり、ペルソナ作成の専門家です。
以下の情報に基づいて、私たちのターゲット顧客となり得る具体的な「価値中心ペルソナ」の案を1~2名作成してください。
ペルソナには、名前、年齢、職業、家族構成などの基本的な属性情報に加え、特に彼/彼女が抱える「ジョブ(機能的・感情的・社会的)」「悩み(ペイン)」「望み(ゲイン)」、価値観、情報収集行動などを具体的に記述してください。
ペルソナが実在の人物のようにイメージできるよう、ストーリー性も持たせてください。
# ペルソナの基盤となる情報
* ターゲット顧客が抱える主要な「ジョブ(悩み・望み)」: [セクション4などで発見したジョブを記述。機能的・感情的・社会的側面も意識して]
* 想定される顧客層の属性(分かっている範囲で): [年齢層、性別、職業、ライフスタイルなどの情報]
* 自社の商品・サービス(またはその構想): [ペルソナが利用することを想定する商品・サービス]
* その他参考情報(顧客インタビューの抜粋、市場調査データなど): [あれば記述]
# 出力形式
* ペルソナごとに以下の項目を含めてください:
* 名前(架空)
* 顔写真のイメージ(説明文で)
* 基本属性(年齢、性別、職業、家族構成、居住地など)
* ライフスタイル・価値観
* 抱える主要なジョブ(機能的・感情的・社会的)
* 具体的な悩み(ペイン)と望み(ゲイン)
* 情報収集の方法・利用メディア
* (自社サービスへの)期待や購買決定要因
* その人となりが分かる短いストーリー or 日常風景
使い方ポイント
AIが生成したペルソナは、あくまで「叩き台」です。
必ずチームで議論し「本当にこんな人いるかな?」「もっとこういう悩みもあるのでは?」と、よりリアルで共感できる人物像へと修正・具体化していくプロセスが最も重要です。AIに複数の異なるタイプのペルソナ案を出してもらい、比較検討するのも良いでしょう。
■ペルソナの詳細を肉付けする
AIの案やチームでの議論を元に、さらに具体的な情報を追加し、ペルソナ像を完成させます。(属性情報、価値観、行動パターンなど)
顔写真や名前をつけより実在感を高めるとより理解しやすくなります。これもAIで画像生成してもらうと良いでしょう。
■ストーリーを描く
そのペルソナの日常や、あなたのサービスを必要とする場面を物語として描いてみます。
ペルソナを作る際は、都合の良い理想像にしないこと、可能であれば複数の異なるジョブを持つペルソナを設定することなどもポイントです。
6. ペルソナから、注力すべき「ターゲット顧客」へ
さて、価値中心のペルソナを描くことで、あなたの理想的な顧客像がかなり具体的になったはずです。
もしかしたら、異なるジョブを持つ複数のペルソナができたかもしれません。
ここで一つ重要なステップがあります。
それは、「これらのペルソナ(が代表する顧客グループ)の中で、自社はどこに最も注力すべきか?」という戦略的なターゲット選定です。
ペルソナはあくまで、顧客理解を深めるための「代表選手」。
実際に事業のリソース(ヒト・モノ・カネ・時間)を投下する相手を選ぶ際には、いくつかの視点から評価し、優先順位をつける必要があります。
■ターゲット選定の主な評価基準(例)
- 市場性
その悩み(ジョブ)を持つ人は、事業として成り立つだけの規模がいるか? 市場は成長しているか?
- 悩みの切実度
その悩みは深く、解決のためにお金を払う意欲は高いか?
- アクセス可能性
その顧客グループに、あなたのメッセージや商品を効率的に届けることができるか?
- 自社の強みとの適合性(超重要!)
あなた(自社)の強みが、その顧客のジョブ解決に本当に活かせるか? 競合よりも上手くやれるか?
- 競合状況
その市場には、どのような競合が、どれくらいいるか?簡単に参入できるか?
これらの基準で各ペルソナ(顧客セグメント)を評価し「自社が最も価値を提供でき、かつ事業として成功する可能性が高い」と判断できるターゲットを、まず優先してアプローチしていくことが、特にリソースの限られる中小企業や創業者にとっては重要になります。
「ペルソナを描くだけでなく、そこから優先する相手を選ぶ視点が必要だ」ということです。
7. まとめ:顧客の「ジョブ」理解が、選ばれる価値を生む
今回は、「属性」だけではない、顧客の「ジョブ(進歩)」に焦点を当てた本質的な顧客理解の方法
そのジョブを多面的に捉える3つの側面(機能的・感情的・社会的)、そしてそれを具体的な「価値中心ペルソナ」として描き、さらに注力すべきターゲットを見定める視点についてお話ししました。
AIを活用してこれらのプロセスを支援する方法もご紹介しましたね。
第2回で発見したあなた(自社)の「強みの元」を活かすためには、まず「誰の、どんなジョブを解決するのか?」を明確に定める必要があります。顧客の「ジョブ」を深く理解し、具体的なペルソナとして描き出すこと。
これこそが、競合の中からあなたの商品・サービスが「選ばれる理由」=「独自の価値提案」を生み出すための、揺るぎない土台となります。
次回、【第4回】「価値提案を磨く:顧客が得たい成果を言語化する方法」では、いよいよ、この顧客理解とあなたの強みを掛け合わせ、顧客の心に響く「価値」を具体的にどう創り出し、言葉にしていくのかを探求します。
今回考えた「顧客像」を胸に、次のステップへ進みましょう!