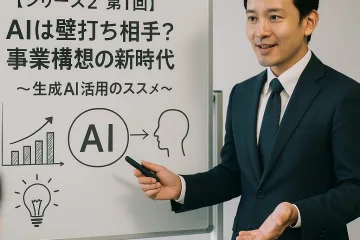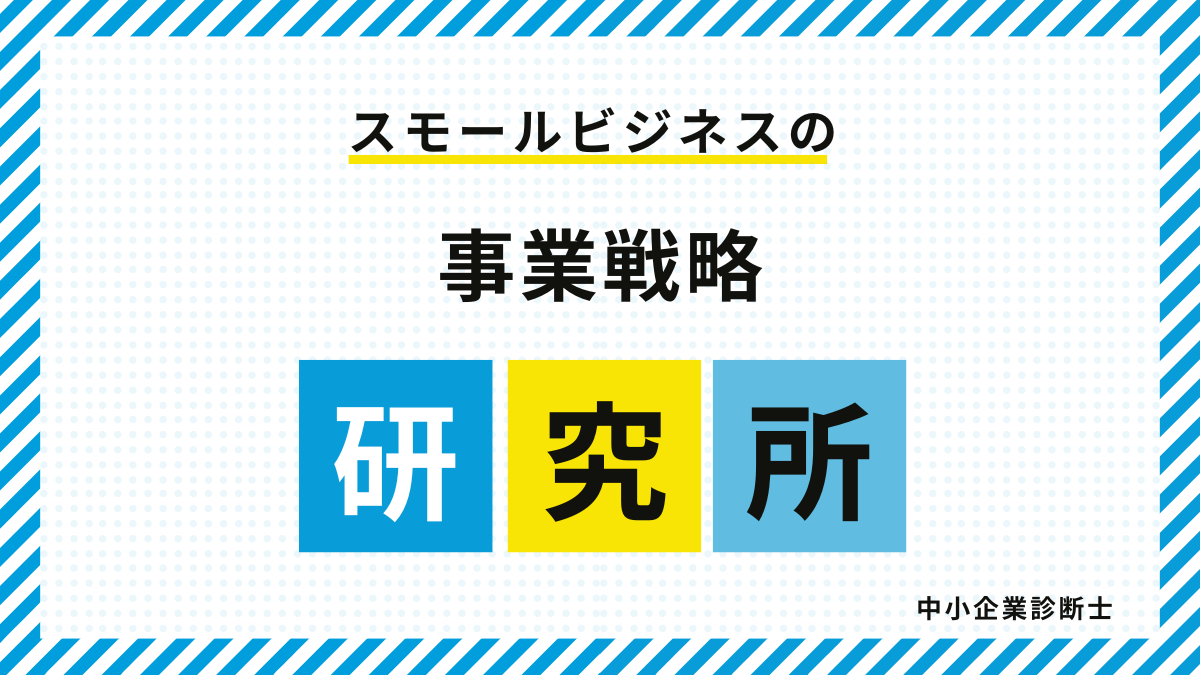
コスト構造を理解し、収益の流れ(RS)とのバランスを考えることなしには、ビジネスの利益を設計し、持続可能性を確保することはできません。
まさに、ビジネスモデル全体を陰で支える『縁の下の力持ち』と言えるでしょう。
皆さんこんにちは!事業構想×生成AI活用アドバイザー(中小企業診断士)の津田です。
未来を描く羅針盤を手に入れる旅、最終回となりました。
前回(第11回)は、自社の力を最大化する『不可欠な協力者』であるキーパートナー(KP)について考え、BMC(ビジネスモデルキャンバス)の左側、「舞台裏」を構成するキーリソース(KR)、キーアクティビティ(KA)、キーパートナー(KP)の3つのブロックが出揃いました。
さて、これでBMCの9つのブロックのうち、8つまでが埋まりました。
いよいよ今回は、最後のブロックであり、ビジネスモデル全体の『土台』を支える「コスト構造(Cost Structure: CS)」に焦点を当てます。
目次
- 1. はじめに ビジネスモデルを支える『縁の下の力持ち』
- 2. コスト構造(CS)とは? – ビジネスモデルを動かす『費用』の全体像
- 3. コストはどこから来る? – KR・KA・KPとの密接な関係
- 4. コスト構造のタイプを知る – あなたのビジネスは『安さ』追求型?『価値』追求型?
- 5. 主なコストの種類を理解する – 費用の性質を知る
- 6. 『キーコスト』の見極め – あなたのビジネスで最も大きな費用は?
- 7. 収益の流れ(RS)とのバランス – 利益を生む設計へ
- 8. 事例で考える - コスト分析から利益設計への4ステップ –
- 9. 【AI活用ヒント】コスト構造 4ステップ分析支援 AIプロンプト案
- 10. Miraiz とコスト構造の最適化・利益設計支援
- 11. まとめ
1. はじめに ビジネスモデルを支える『縁の下の力持ち』
コスト構造は、これまで設計してきた全ての要素、
価値提案(VP)を創り出し(KR, KA, KP)、顧客(CS)に届け(CH)、関係を築き(CR)、収益(RS)を得るといったこれらの活動全体を実行した結果として、必然的に発生する『費用』の全体像を示します。
ともすると、コストは「低い方が良い」と単純に考えがちですが、ビジネスモデルにおけるコスト構造は、もっと奥が深いものです。
それは単なる経費リストではなく、どのような価値を提供するために、どこに重点的に投資しているかという、
あなたのビジネスの戦略そのものを反映する鏡でもあります。
このコスト構造を理解し、収益の流れ(RS)とのバランスを考えることなしには、ビジネスの利益を設計し、持続可能性を確保することはできません。
まさに、ビジネスモデル全体を陰で支える『縁の下の力持ち』と言えるでしょう。
今回のゴールは、このコスト構造とは何か、主要なコストがどこから発生するのか、コストに対する戦略的な考え方、そして最終的に利益を生むための設計について学ぶことです。
そして、単に理解するだけでなく、分析結果を具体的なアクションに繋げていくことを目指します。
それでは、ビジネスの土台を、一緒に見つめていきましょう!
2. コスト構造(CS)とは? – ビジネスモデルを動かす『費用』の全体像
■CSブロックの定義
ビジネスモデルキャンバスの9番目のブロックであるコスト構造(CS)は、ビジネスモデルを運営していく上で発生する、最も重要なコストのすべてを記述する場所です。
■「キーコスト」への焦点
会計上の全ての費用を細かくリストアップするというよりは、そのビジネスモデルの性質を決定づける、あるいは金額的にインパクトの大きい『主要なコスト(キーコスト)』に焦点を当てて記述します。
後ほど、このキーコストの見極め方についても触れます。
■なぜ分析するのか?
事業継続に必要な資金額を把握するため、適切な価格設定(RS)の根拠とするため、コスト削減の可能性を特定するため、そして最終的に「このビジネスモデルは儲かるのか?」という収益性を評価・改善するために不可欠だからです。
3. コストはどこから来る? – KR・KA・KPとの密接な関係
では、コストは具体的にどこから発生するのでしょうか? その大部分は、前回までに見てきたBMCの「舞台裏」の要素、つまりキーリソース・キーアクティビティ・キーパートナーと密接に関係しています。
■キーリソース(KR)に起因するコスト
例:良い人材を雇うための人件費、店舗やオフィスを借りる家賃、設備を導入・維持するための減価償却費やリース料、ブランドを構築するための広告宣伝費(知的資産形成)、事業に必要な運転資金の調達コスト(支払利息など)。
■キーアクティビティ(KA)に起因するコスト
例:製品を作るための原材料費・製造費、サービスを提供するための人件費や外注費、顧客を獲得するためのマーケティング・販売促進費、新しい価値を生むための研究開発費、ECサイトを運営するためのシステム維持費など。
■キーパートナー(KP)に起因するコスト
例:商品を仕入れるための仕入費用、製造を委託するための外注費、販売を代理してもらうための販売手数料、提携先へのライセンス料など。
このように、価値提案を実現するためにどのようなリソースを使い(KR)、どのような活動を行い(KA)、誰と協力するか(KP)という、これまで設計してきた選択が、そのままコスト構造(CS)に直接反映されます。
4. コスト構造のタイプを知る – あなたのビジネスは『安さ』追求型?『価値』追求型?
ビジネスモデル全体のコストに対する考え方には、大きく2つの方向性があります。自社がどちらに近いかを意識することは、コスト管理や価格設定の戦略を立てる上で重要です。
① コスト主導型
できる限りコストを抑えることを最優先するアプローチ。無駄を徹底的に省き、低価格な価値提案を実現します。標準化、自動化、アウトソーシングなどを多用し、効率性を追求します。
■目指す戦略例
オペレーション・エクセレンス(業務の卓越性)
■身近な例
・地域最安値を前面に出しているクリーニング店や、薄利多売の定食屋さん(徹底した効率化や仕入れ努力で低価格を実現)
・特定の定型業務(データ入力など)を、低価格・スピード重視で請け負う個人事業主(自身の効率性と低い固定費で勝負)
・価格比較サイトで常に最安値帯を狙う、特定のジャンルに特化した小規模EC事業者(仕入れと運営効率を極限まで追求)
② 価値主導型
高品質な価値提案や、特別な顧客体験を提供することを優先するアプローチ。
コスト削減よりも、価値を高めるための投資(高品質なリソース、特別な活動)を重視します。プレミアムな価格設定が前提となることが多いです。
■目指す戦略例
プロダクト・リーダーシップ(製品の優位性)やカスタマー・インティマシー(顧客親密性)
■身近な例
・厳選された特別な素材と独自の製法にこだわる、町の小さなパン屋さんやケーキ屋さん(価格は高くても、味と品質でファンを掴む)
・顧客一人ひとりの課題に深く寄り添い、紹介を中心に活動するコンサルタントやコーチ、デザイナー(高い専門性と信頼関係で価値を提供)
・店主の個性やセレクト、集まる人々で独自のコミュニティが生まれているカフェやバー、雑貨店(価格以上の体験価値を提供)
・他では修理できない特殊な機械を直せる、地域で頼りにされる町工場(ニッチな技術力で高い価値を提供)
・独自のデザインや世界観で熱心なファンを持つハンドメイド作家(作品の独自性やストーリーで勝負)
多くのビジネスは、この両方の要素を併せ持ちますが、どちらの方向性をより強く意識するかによって、コストに対する考え方や管理方法が変わってきます。
例えば、「価値主導型」だからといってコストを無視して良いわけではなく、提供価値に見合った範囲で効率化を図る必要はあります。
5. 主なコストの種類を理解する – 費用の性質を知る
コスト構造をより深く理解するために、費用の性質による分類を見てみましょう。
① 固定費 (Fixed Costs): 売上高や生産・販売量の増減に関わらず、比較的一定額が発生するコスト
例: オフィスの家賃、正社員の人件費(給与)、設備の減価償却費、定額のリース料、サーバー維持費など
② 変動費 (Variable Costs): 売上高や生産・販売量に比例して増減するコスト
例: 商品の仕入原価、製品の原材料費、販売手数料、成果報酬型の人件費、梱包・配送料など
(参考)規模の経済 (Economies of Scale)
生産量や仕入量が増えるほど、単位あたりのコスト(固定費の分散効果や仕入れ割引など)が低下する効果。たくさん作れば作るほど、1個あたりのコストが安くなるイメージです。
■身近な例
・パン屋さんが、一度に多くのパンを同じ窯で焼くことで、パン1個あたりの光熱費や窯の減価償却費を下げる。
・飲食店が、特定の野菜をまとめて大量に仕入れることで、仕入れ単価の割引を受ける。
(参考)範囲の経済 (Economies of Scope)
複数の製品やサービスで、リソースや活動(例:販売網、ブランド、製造ライン、ノウハウ)を共有・活用することで得られるコストメリット。
1つの資源で複数のことをまかなうことで、トータルコストを下げるイメージです。
■身近な例
・カフェが、昼の営業で使っている店舗スペースや厨房設備、一部スタッフを活用して、夜はバーとしても営業する。
・手作り石鹸メーカーが、石鹸製造で得たアロマや天然素材の知識(知的リソース)を活かして、アロマキャンドルやバスソルトといった新商品を比較的低コストで開発・販売する。
・コンサルタントが、ある顧客向けに作成した汎用的な資料やノウハウを、別の顧客にも(一部カスタマイズして)活用する。
自社のコスト構造が固定費・変動費のどちらの比率が高いか、規模や範囲の経済が働く可能性があるかなどを理解することは、後述する損益分岐点の計算や、事業拡大時のコスト予測、価格設定戦略を立てる上で役立ちます。
6. 『キーコスト』の見極め – あなたのビジネスで最も大きな費用は?
BMCのコスト構造(CS)ブロックには、全ての費用を書き出すのではなく、ビジネスモデルの性質を特徴づけ、全体の費用構造に大きな影響を与える『最も重要なコスト(キーコスト)』を特定して記述します。
■見極め方のヒント
■KR, KA, KPの分析
・どのキーリソースの獲得・維持に最もコストがかかるか?(例:人件費? 賃料? 研究開発費?)
・どのキーアクティビティの実行コストが大きいか?(例:製造原価? 広告宣伝費?)
・どのキーパートナーへの支払いが大きいか?
■財務諸表の分析(既存事業の場合)
・損益計算書などで、金額の大きい費目や、変動の大きい費目は何か?
■固定費 vs 変動費
・自社のコスト構造はどちらの比率が高いか? 収益変動に対する影響は?
キーコストを特定することで、コスト管理の重点項目や、コスト削減のターゲットが見えてきます。
7. 収益の流れ(RS)とのバランス – 利益を生む設計へ
ビジネスモデル全体の最終的な健全性は、このコスト構造(CS)と収益の流れ(RS)のバランスで決まります。
「収益の流れ(RS) > コスト構造(CS)」となって初めて利益が生まれ、事業は持続可能になります。
■価格設定との連動
収益(RS)は「価格×数量」で決まります。
価格は、コスト(CS)を確実にカバーし、さらに顧客が納得する価値(VP)に見合っている必要があります。
コスト構造を理解することは、適切な価格設定の前提となります。
■戦略との整合性
コスト主導型なら低価格(RS収益の流れ)を実現できる徹底した低コスト構造(CS)が、価値主導型ならプレミアム価格(RS収益の流れ)を支える高コスト(高品質KR/KAへの投資)構造(CS)が必要です。ビジネスモデル全体で一貫性が取れているかを確認しましょう。
■損益分岐点の意識
最低限どれだけの収益(RS)があれば、コスト(CS)を賄えるのか(利益がゼロになる点=損益分岐点)を把握することは、事業計画や目標設定の基本です。(計算例は次のセクションで見てみましょう)
■継続的な見直し
市場環境や競争状況、自社のステージの変化に合わせて、コスト構造も収益の流れも常に見直し、最適化を図る必要があります。
8. 事例で考える - コスト分析から利益設計への4ステップ –
これまでに学んだコスト構造の考え方を踏まえ、「結局、何をすればよいのか?」というアクションに繋げるプロセスを見ていきましょう。
カフェ、パーソナルトレーナー、手作り石鹸メーカーを例に、4つのステップで分析を進めます。
(8-1) 事例1:カフェ「Third Place」の場合
VP(例): 「自宅でも職場でもない、心地よい第3の居場所」
ステップ① キーコスト特定
このカフェの主要なコスト(キーコスト)は何でしょうか?
おそらく、店舗の家賃(固定費)、バリスタなどの人件費(固定費中心)、そしてコーヒー豆や食材の仕入れ費(変動費)が大きな割合を占めると考えられます。
ステップ② コスト性質分析
固定費(家賃、人件費)の割合が高めになりそうです。
価値提案(空間、コーヒーの質、接客)を考えると、安さよりも価値を追求する「価値主導型」のアプローチに近いでしょう。
そのため、質の高いリソース(良い立地、良い人材)への投資は、ある程度必要と判断されます。
ステップ③ 収益性チェック(損益分岐点)
ここで簡単な損益分岐点の計算例を示します。
例えば、月の固定費が合計50万円、変動費率(売上に対する原材料費などの割合)が30%だとすると、限界利益率(1-変動費率)は70%です。
損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ 限界利益率 = 500,000円 ÷ 0.70 ≒ 約71.5万円
つまり、月71.5万円以上の売上がないと赤字ということです。
この売上目標は、想定する客単価と客数から見て現実的でしょうか?
利益を出すには、さらにどれだけの売上が必要でしょうか?
ステップ④ 最適化・戦略検討
この分岐点をクリアし、利益を出すためにどうするか?
・客単価を上げる(高付加価値メニュー、セット販売)
・来店客数を増やす(マーケティング強化、リピート促進)
・変動費率を下げる(食材ロスの削減、仕入れ交渉 ※品質は維持)
・固定費(特に家賃)が提供価値に見合う投資と言えるかを再検討する
などの打ち手が考えられます。価格設定は適切かも重要な論点です。
(8-2) 事例2:パーソナルトレーナーの場合
VP(例): 「科学的根拠に基づき、目標達成に寄り添うマンツーマン指導」
ステップ① キーコスト特定
このビジネスで最も大きなコストは、トレーナー自身の労働時間に対する報酬(目標月収など)です。
これを仮に月30万円と設定します。
その他、提携ジムへの支払い(月5万円の固定)、集客のための広告費やツール利用料(月3万円)、保険料など(月2万円)がかかるとします。
これらが主要な固定費(合計40万円)となります。
セッションごとの交通費や消耗品などの変動費は比較的小さい(例:1セッションあたり500円)と仮定します。
ステップ② コスト性質分析
上記の通り、自身の目標収入を含めた固定費の割合が非常に高い構造です。提供する価値は専門性や成果であり、典型的な「価値主導型」と言えるでしょう。
ステップ③ 収益性チェック(損益分岐点)
1セッションあたりの価格を8,000円と設定した場合、1セッションあたりの変動費500円を引いた限界利益は7,500円です。
目標月収を含めた月間の固定費40万円を、この限界利益7,500円で回収するには、何セッション必要でしょうか?
損益分岐点セッション数 = 固定費 ÷ 1セッションあたり限界利益
400,000円 ÷ 7,500円/セッション ≒ 53.3セッション
つまり、月に約54セッション(週に13〜14セッション)を提供して、初めて目標月収を含めたコストを回収できる計算になります。
これに加えて利益を出すには、さらに多くのセッションが必要です。このセッション数は現実的に達成可能でしょうか?
ステップ④ 最適化・戦略検討
もし月54セッションが厳しい場合、どうするか?
・集客コスト(月3万円)の費用対効果を見直し、より効率的な方法(例:既存顧客からの紹介促進、SNSでの専門性発信強化)で新規顧客を獲得・維持する。
・自身の専門性や実績(提供価値)をさらに高め、セッション単価(現在8,000円)の引き上げを検討する(例:9,000円にすれば分岐点は約45セッションに下がる)
・あるいは、より高単価の複数回コースやプログラムを設計する。
・自身の稼働率(指導可能な時間)を上げる工夫はできないか?(例:効率的な予約システムの導入、オンライン指導の組み合わせ)
・固定費(提携ジム料など)を削減できないか交渉する、あるいは別の方法を検討する。
(8-3) 事例3:手作り石鹸メーカーの場合
VP(例): 「天然素材の、肌に優しく心も満たす手作り石鹸」
ステップ① キーコスト特定
主要コストは、高品質な原材料費(変動費)、製造に必要な光熱費や工房の家賃(固定費)、自身の労働時間(またはスタッフ人件費、固定費/変動費)、パッケージ費用(変動費)、ECサイト運営費や販売手数料(固定費/変動費)などが挙げられます。
ここでは仮に、月間の固定費合計を15万円とし、石鹸1個あたりの変動費(材料費、パッケージ代など)を300円とします。
ステップ② コスト性質分析
原材料費などの変動費の比率がある程度高くなりそうです。
VP(原料や製法へのこだわり)から「価値主導型」の側面が強いですが、製造プロセスを効率化するなど「コスト主導型」のアプローチ(特に変動費削減)を取り入れる余地もあります。
ステップ③ 収益性チェック(損益分岐点)
石鹸1個あたりの販売価格を1,000円と設定した場合、1個あたりの変動費300円を引いた限界利益は700円です。
月間の固定費15万円を、この限界利益700円で回収するには、何個販売する必要があるでしょうか?(※ここでは、簡単化のため、自身の目標収入は利益から得るものとし、固定費には含めていません。)
損益分岐点販売個数 = 固定費 ÷ 1個あたり限界利益
150,000円 ÷ 700円/個 ≒ 214.3個
つまり、月に約215個の石鹸を販売して、初めて固定費を回収できる計算になります。
これ以上の販売数が利益となります。
この販売個数は、製造能力や現在の販路から見て達成可能でしょうか?
ステップ④ 最適化・戦略検討
利益を増やす、あるいは分岐点を下げるためにどうするか?
・変動費(原材料費)の削減: 仕入先との交渉、共同仕入れ、代替可能な材料の検討(ただしVPである品質は維持)
・固定費の削減: 製造プロセスを効率化し、時間あたりの生産量を増やして労務費(固定費とみなす場合)を削減する。
・販売価格の引き上げ: ブランド価値(ストーリー、デザイン)を高め、より高い価格(例:1,200円なら分岐点は約167個に下がる)でも顧客が納得するように訴求する。
・販売数量の増加: 新しい販売チャネル(例:委託販売先、イベント出展、ギフト需要開拓)を開拓する。
(8-4) まとめ
このように、どのビジネスであっても、コスト構造を4つのステップで分析し、具体的な改善アクションや戦略に繋げていくことが、利益を生み出し事業を持続させる鍵となります。
9. 【AI活用ヒント】コスト構造 4ステップ分析支援 AIプロンプト案
# 命令 (Command)
あなたは経験豊富なビジネス戦略コンサルタントであり、特に中小企業のコスト分析と利益改善に詳しい専門家です。
以下の私のビジネス情報に基づき、コスト構造の分析と戦略的検討を、下記の4つのステップに沿って手伝ってください。
# 私のビジネス情報 (My Business Information)
* **事業概要・価値提案(VP):** [例:天然素材にこだわった手作り石鹸を主にECサイトで販売。肌への優しさと豊かな香りで、日々の癒やしを提供。]
* **主要なキーリソース(KR):** [例:独自の石鹸レシピ・製造ノウハウ、高品質オーガニック原料、ブランドイメージ。]
* **主要なキーアクティビティ(KA):** [例:石鹸製造、品質管理、ECサイト運営・マーケティング、梱包・発送。]
* **主要なキーパートナー(KP):** [例:特定オーガニック原材料供給業者、パッケージデザイナー、ECプラットフォーム事業者。]
* **想定される収益の流れ(RS)と価格:** [例:石鹸1個あたり1000円で販売。月間目標販売数は500個を想定。]
* **想定される主なコスト(月間見積もり):**
* **固定費(FC)合計:** [例:約15万円(工房家賃5万、人件費(自分含む)8万、サイト維持費2万など)]
* **商品1単位あたり変動費(VC):** [例:石鹸1個あたり約300円(材料費200円、パッケージ代50円、発送関連費50円など)]
# 実行してほしいこと(4ステップでの分析支援) (Tasks to Perform - 4-Step Analysis Support)
**ステップ①:キーコスト特定 (Identify Key Costs)**
* 上記の情報(特にKR, KA, KPとコスト見積もり)から、このビジネスモデルにおいて**最も重要と思われるコスト(キーコスト)**を特定し、それが主に**固定費か変動費か**を指摘してください。
**ステップ②:コスト性質分析 (Analyze Cost Nature)**
* 特定されたキーコストとVPに基づき、このビジネスモデルのコスト構造は**「コスト主導型」と「価値主導型」のどちらの傾向が強いか**、理由と共に分析してください。
**ステップ③:収益性チェック(損益分岐点の検討)(Check Profitability - Break-Even Consideration)**
* 提供されたコストと収益の見積もりから、**おおよその損益分岐点(例:月間販売個数)**を計算または推定し、月間目標販売数(500個)と比較して、その**実現可能性や収益性**についてコメントしてください。(計算が難しい場合は、計算方法の考え方を示してください。)
**ステップ④:最適化・戦略検討 (Consider Optimization/Strategy)**
* ステップ①~③の分析を踏まえ、このビジネスが利益を確保・向上させるために考えられる**具体的な「最適化・戦略」**の選択肢をいくつか提案してください。提案には以下のような視点を含めてください。
* コスト削減や効率化の可能性(VPを損なわずに)
* 価格設定の見直しの可能性
* 収益増(販売数量増、客単価UPなど)のための施策との連携
* コスト構造タイプ(価値/コスト主導)と整合した戦略か # 出力形式 (Output Format)
* 上記の4つのステップごとに、分析結果や提案を分かりやすく記述してください。
10. Miraiz とコスト構造の最適化・利益設計支援
私たちMiraizは、クライアント様のビジネスモデル全体を俯瞰し、KR・KA・KPから発生するコスト構造を明確化します。
収益の流れ(RS)とのバランスを評価し、利益を生み出すための価格設定やコスト削減の可能性について、具体的な検討をサポート。
価値提案(VP)を損なわずにコストを最適化し、持続可能なビジネスモデルを設計するための戦略的なアドバイスと可視化支援を行います。
11. まとめ
今回は、BMC最後のブロック「コスト構造(CS)」について、その重要性、KR・KA・KPとの関連、コスト主導型vs価値主導型のアプローチ、主なコストの種類、そして収益(RS)とのバランス(利益創出)の考え方、さらには分析後に取るべき具体的な4ステップ(キーコスト特定→性質分析→収益性チェック→最適化戦略)を学びました。
これで、ビジネスモデルキャンバスの9つのブロック全ての要素が出揃い、あなたのビジネスの全体像を描く「未来図」が完成しました!
長い旅でしたが、本当にお疲れ様でした!
次シリーズでまたお会いできること楽しみにしています!