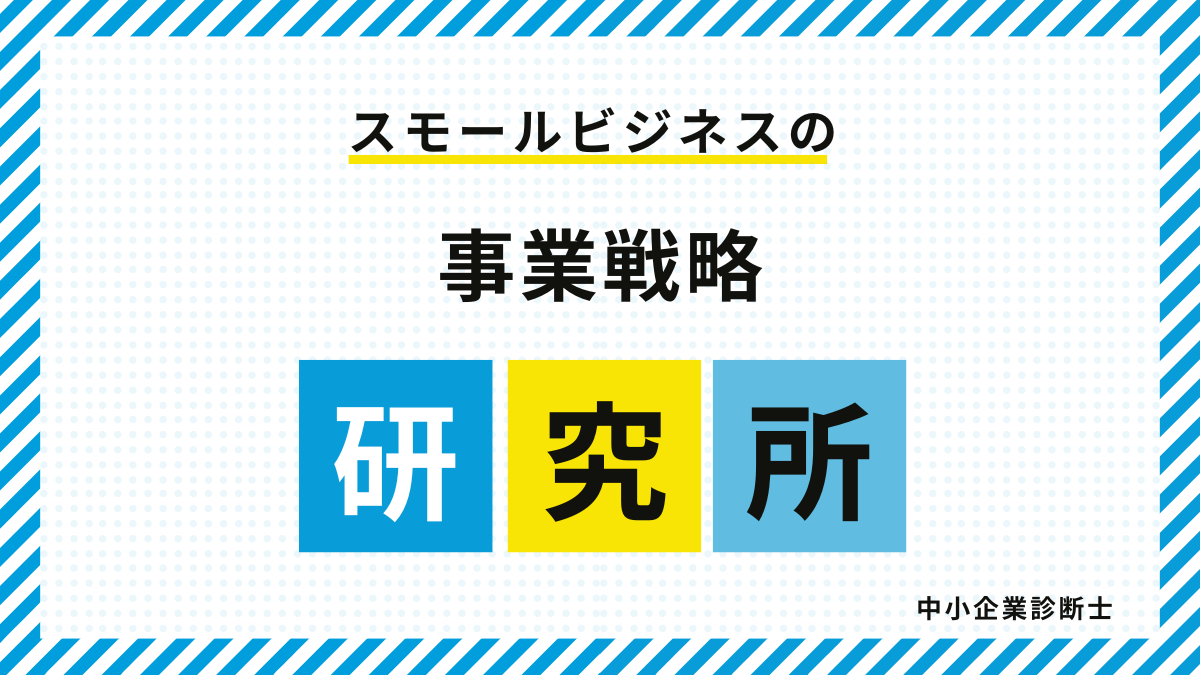
その「もやもや」した悩み、いつまで続けますか? 事業の「迷走」から抜け出し、「次の一手」を見つけるために。

「自分の技術で起業したけど、どうやって売ればいいか分からない…」
「販路を変えたいけど、具体的な方法が見えない…」
「お客さんが来ない…このままではまずい…」
「新しい事業を考えているが、考えがまとまらずモヤモヤする…」
日々の課題に忙殺される中で、もしあなたが「次に何をすべきか」という確かな道筋を見失いかけているとしたら。今こそ、あなたの事業の未来を照らす『羅針盤』=事業構想を、具体的な『言葉』にする時かもしれません。
このブログは、そんなあなたと一緒に、事業の進むべき道、すなわち『事業構想』を明確にし、自信を持って未来へ踏み出すための『未来図』を描きませんかというご提案です。
皆さんこんにちは、事業構想×生成AI活用アドバイザー(中小企業診断士)の津田です。
この連載では、全10回にわたり、事業構想を「言語化・可視化」することの重要性と具体的な方法、そして私が提供する、生成AIを活用した事業構想の言語化・可視化の伴走型サポート「Miraiz(未来図)」についてお伝えしていきます。
事業構想とは「自分がやりたい事業について、その目的や中身を具体的にイメージし、明確な言葉や図で表現すること」で、しっかりと言語化できると、行動が明確になり未来への道筋が見えてきます。
まずはじめに、なぜ私が事業構想に関するブログを書こうと思ったのかを述べたいと思います。
1.その悩み、根本原因はどこにある? ~未来を描く羅針盤を求めて~
「自分の技術やノウハウを活かして起業したけれど、どうやって売ればいいのか分からない。ホームページ? SNS? 価格設定? 何から手をつければ…」
「長年頼ってきた取引先の動きが鈍く、直接お客様に販売したいけれど、どうアプローチすれば良いか見当もつかない…」
「夢だった自分のお店を開いたのに、お客さんがなかなか来てくれない。このままでは資金が… 何か手を打たないと…」
もしあなたが今、このような具体的な課題に直面し、「次に何をすべきか?」と悩んでいるとしたら。あるいは、今は順調でも、「このままで、5年後、10年後も大丈夫だろうか?」「もっと自社の価値を高めるために、新しい挑戦をすべきでは?」といった漠然とした期待や不安を心のどこかで感じているとしたら。
日々、目の前の売上や資金繰り、顧客対応、従業員のこと… 経営者や創業者の方々は、本当に多くの課題と向き合っていらっしゃいますよね。
しかし、その一つ一つの課題への対処に追われる中で、もしかしたら、もっと根本的な『羅針盤』を見失ってはいないでしょうか?
このブログは、そんなあなたと一緒に、事業の進むべき道、すなわち『事業構想』を明確にし、自信を持って未来へ踏み出すための『未来図』を描く旅への招待状です。
2. 私が「事業構想の言語化」にこだわる理由
これまで多くの経営者の方々とお会いする中で、ご相談いただくのは「今起きている問題」への対処法が多いです。当然のことです。
「まずやってみる」「走りながら考える」というスタンスで、とにかく具体的な行動から入る方も少なくありません。スピード感を持って事を進める上で、それ自体は決して間違いではないと私も思います。
しかし、その先で「あれ?思ったようにいかないぞ」という壁にぶつかることも、残念ながら多く、そのためにご相談を頂きます。
「やってみたら、想定外のコストがどんどん膨らんでしまった」
「自信を持って世に出した商品やお店なのに、お客様に全然響かない」
「ホームページもSNSも頑張っているはずなのに、なぜか成果が出ない…」
そして、「一体、何をすればいいんだろう?そもそも何をやりたかったんだろう・・。」と、具体的な打ち手が見えなくなり、途方に暮れてしまう。
出口が見えない暗闇の長いトンネルの中にいて、色々と試し、焦り、悩み、もがく中で、前に行っても後ろに戻っても光が見えない。そんな気持ちになってしまうことがありませんか?
そんな時、多くの方は
「ホームページの内容が悪いのかな?」
「インスタのやり方がまずいのかな?」
「価格が高いのかな??」と、目に見える『やり方』(戦術)の部分に原因を探そうとします。
ですが、私が様々なケースを見てきた中で感じるのは、問題の根っこは、もっと深い『そもそも』の部分にあることが多い、ということです。
『そもそも、なぜ、この事業を考えたのか?どうなりたいと望むのか?』
『そもそも、どんな望みを持ったお客様に、どんな独自の価値を届けたいのか?』
『競合他社はどんなことをしていて、自社はそれとどう違い、なぜお客様に選んでいただけるのか?』
…こうした事業の根幹をなす問いに対して、実は、はっきりとした答え(=事業構想)を持てていない、明確な言葉になっていないケースが多いと感じています。
だからこそ、根本的な『羅針盤』がないまま、目先の戦術だけをあれこれ変えようとしても、なかなか本質的な解決には至らない。
これが、私が「まず事業構想を言語化・可視化しましょう」とお勧めする、大きな理由の一つなのです。
3. 「言葉」が、人と組織を動かす
事業構想が明確でない状態では、先ほどの『そもそも』の問いに、自信を持って答えることは難しいでしょう。
しかし、ひとたび構想が言語化・可視化され、経営者自身が深く腹落ちすると、そこから驚くほどのポジティブな変化が連鎖的に生まれます。
- 経営者の変化
まず、経営者ご自身の迷いが消え、目の輝きが変わります。「これだ!」という軸が定まることで、やるべきこと、そして『やらないこと』が驚くほど明確になります。
結果として、行動に無駄がなくなり、限られたエネルギーとリソースを最も重要な一点に集中できるようになる。「早くこれを実現したい!」と、行動したくてウズウズしてくる。そんな状態になります。(確信)
- 事業活動の一貫性
そして、その明確な構想は、あらゆる事業活動に反映されます。
ホームページに書かれる言葉、マーケティングのメッセージ、営業での語り口、商品や店舗のデザイン…そのすべてに一本の筋が通り、「なぜ自社が選ばれるのか」という独自の価値が一貫して、力強く伝わるようになります。
- 競合への理解と自信
闇雲に競合を恐れるのではなく、競合が何をやっているかを冷静に把握した上で、「自社はここが違う」「だから選ばれるんだ」と、その独自の立ち位置と価値を、誰に対しても即座に、自信を持って説明できるようになります。
- 組織の変化(従業員がいる場合)
さらに素晴らしいのは、その変化が組織全体に広がっていくことです。経営者の想いと目指す方向性が、単なる目標数値だけでなく、具体的な言葉やストーリーとして共有されることで、従業員一人ひとりが「自分たちの仕事が、この大きな未来にどう繋がっているのか」という意義を実感できるようになります。
結果として、目標に向かって主体的に、そして何より生き生きと動き出し、組織全体が一体感を持って力強く前進し始めるのです。
私は、この事業構想が明確になることで生まれる『変化』、特に人が輝き、組織が躍動し、未来へ向かって力強く動き出す、その姿を見るのが、本当に大好きなんです。
4. このブログで、みなさまと一緒に創りたい未来
その『人が本来持つ力を解き放つ瞬間』に立ち会い、変化のプロセスをすぐ隣でサポートできること。これこそが、私がこの仕事を通じて最も『楽しい!』と感じる瞬間であり、一番のやりがいです。
ですから、このブログシリーズは、単なる事業構想のフレームワークや作り方の解説書ではありません。
もちろん、具体的な考え方や、生成AIの活用法といった実践的なノウハウもお伝えします。
しかし、それ以上に私が目指しているのは、
事業を志す人の中に眠る「こんなことを実現したい」という熱い想いや、
まだ気づいていないかもしれない「あなた(自社)ならではの強みの元」を一緒に引き出し、
それを「社会や顧客が本当に求める価値」と結びつけ、
あなただけの具体的な「未来図」として言語化・可視化していく、
そのプロセスそのものを伴走者としてサポートすることです。
そして、そのプロセス自体を、私自身が一番「楽しく、ワクワクする」と感じています。
このブログを通じて、そのワクワク感を、ぜひあなたとも共有したいのです。
5. このブログシリーズの概要
この序章に続く本編では、事業構想を言語化・可視化していくための具体的なステップを、全10回(予定)にわたって探求していきます。
【第1回】事業構想の「言語化・可視化」とは何か? (今回の序章で触れたテーマを、より基本から解説します)
【第2回】まずは自分を知る:強みの発見がすべての出発点
【第3回】顧客のニーズを正しく掴む:ペルソナ・セグメント分析の基本
【第4回】価値提案を磨く:顧客が得たい成果を言語化する方法
【第5回】ビジネスモデルキャンバスを使いこなす
…(以降、競合分析、収益モデル、AI活用、事例紹介へと続きます)
各ステップでは、具体的な考え方やワークはもちろん、事業構想のプロセスで「どのように生成AIを活用すれば、思考を加速し、深めることができるか」という実践的なテクニックも、惜しみなくご紹介していく予定です。
6. さあ、未来を描く旅に出かけましょう!
未来は、誰かが与えてくれるものではありません。自らの手で描き、創り出していくものです。 そのための最初の、そして最も重要な一歩が、あなたの事業構想を「言葉」にすること。
もし今、あなたが未来への一歩を踏み出したい、あるいは踏み出すべきだと感じているなら。 ぜひ、このブログと共に、あなただけの輝く「未来図」を描く旅に出かけませんか?
このブログが、その旅のための確かな羅針盤となり、時に励まし、時に新たな視点を提供する、信頼できる伴走者となれれば、これほど嬉しいことはありません。
次回から始まる本編(第1回)で、あなたとお会いできることを楽しみにしています!

